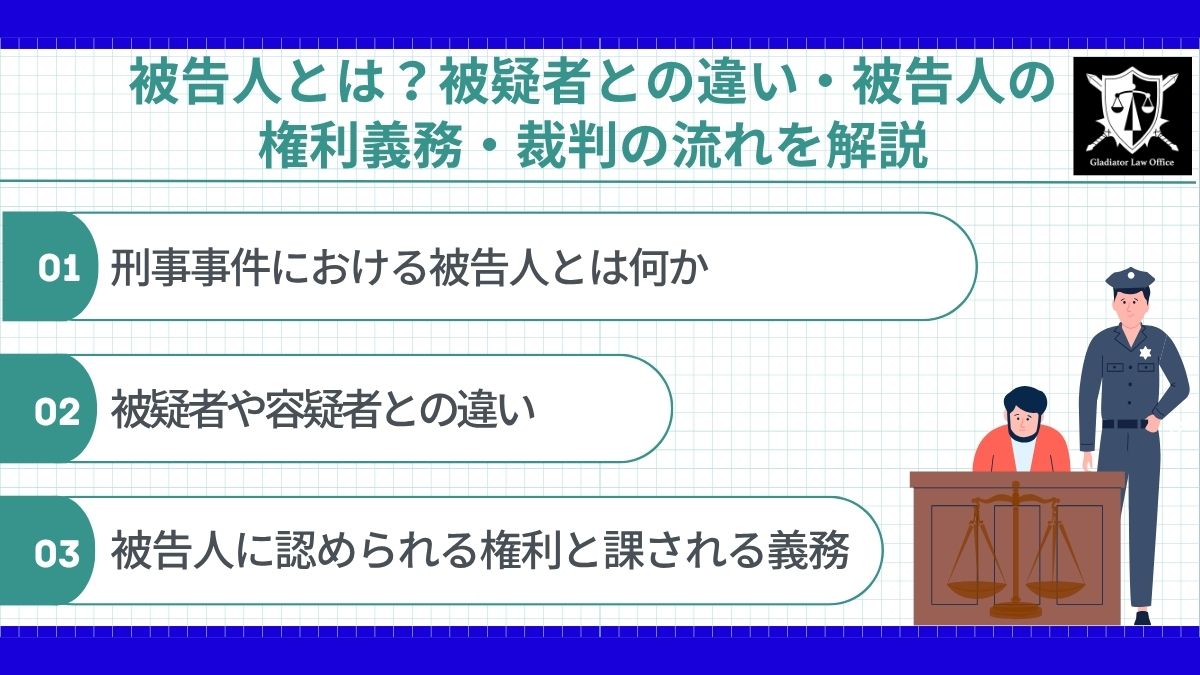「被告人とはどのような立場の人を指す言葉なの?」
「被告人と被疑者の違いは何?」
「被告人にはどのような権利や義務があるの?」
刑事事件のニュースを見ていると「被告人」という言葉をよく耳にします。しかし、この「被告人」という用語が正確にはどの段階の人物を指すのか、被疑者や容疑者とどのように違うのか、意外と知られていないのではないでしょうか。一般的には「逮捕された人」「裁判にかけられている人」といったイメージを持つ方が多いですが、刑事手続の中では明確な意味が定められています。
「被告人」とは、検察官によって正式に起訴され、刑事裁判にかけられている人をいいます。これに対し、起訴前の段階では「被疑者」と呼ばれ、マスコミ報道では「容疑者」という言葉が使われることもあります。さらに、民事裁判での「被告」と混同されることもありますが、両者はまったく異なる立場です。このように「被告人」という言葉ひとつをとっても、刑事手続や法的文脈を理解していないと誤解しやすいのです。
本記事では、
| ・刑事事件における被告人とは何か ・被疑者や容疑者との違い ・被告人に認められる権利と課される義務 |
自分や身近な人が刑事事件に関わってしまった場合に備えて理解しておきたいポイントを整理していますので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
刑事事件における被告人とは?
「被告人」とは、刑事事件において検察官から起訴され、刑事裁判にかけられている人を指す言葉です。つまり、事件を起こしたと疑われて捜査を受ける段階の「被疑者」や、報道でよく耳にする「容疑者」とは異なり、すでに裁判手続に入っている人物を意味します。
刑事裁判は、国家が個人を処罰するという重大な手続です。そのため、誰でもいきなり「被告人」と呼ばれるわけではなく、警察や検察による捜査を経て、検察官が「裁判で有罪を立証できる」と判断した場合にのみ起訴され、その結果「被告人」となります。
このように「被告人」とは、刑事手続のなかで特定の段階にある立場を示す法律用語であり、一般的なイメージ以上に厳密な意味を持っています。
被告人と被疑者・容疑者との違い
刑事事件では「被疑者」「容疑者」「被告人」という言葉が使われますが、それぞれ指す段階が異なります。特に、「被告人」は起訴後の人物を指す点が大きな違いです。
| 法律上の位置づけ | 意味 | 起訴前/起訴後 | |
|---|---|---|---|
| 被疑者 | 法律用語 | 犯罪の嫌疑をかけられて捜査段階にある人 | 起訴前 |
| 容疑者 | 報道用語 | 犯罪の嫌疑をかけられて捜査段階にある人 | 起訴前 |
| 被告人 | 法律用語 | 検察官によって起訴されて刑事裁判の段階にある人 | 起訴後 |
被疑者とは
「被疑者」とは、犯罪を行った疑いがあり、警察や検察から捜査の対象となっている人をいいます。逮捕されていなくても、捜査段階で疑いをかけられている人はすべて被疑者です。法律上の正式な用語であり、起訴される前の段階を示します。
容疑者とは
「容疑者」という言葉は、法律上の正式な用語ではありません。主に報道機関が「被疑者」を指す際に用いるマスコミ用語です。一般の人にとっては「逮捕された人」をイメージしやすい言葉ですが、法的には「被疑者」と同義であり、起訴前の段階を意味します。
被告人と被告との違い
「被告」とは、民事裁判で訴えられた側の当事者を指す用語です。たとえば、損害賠償請求や契約トラブルなどで裁判になった場合に、訴えられた人(あるいは会社)が「被告」となり、訴えた人が「原告」となります。そのため、「被告人」と「被告」という用語は、刑事事件か民事事件かという大きな違いがあります。
ただし、新聞やテレビなどの報道では、刑事事件の裁判でも「被告人」を省略して「被告」と呼ぶケースが多く見られます。これは一般の人にとって耳慣れた表現であり、紙面や放送の都合上、省略されているに過ぎません。
被告人に認められている法律上の権利
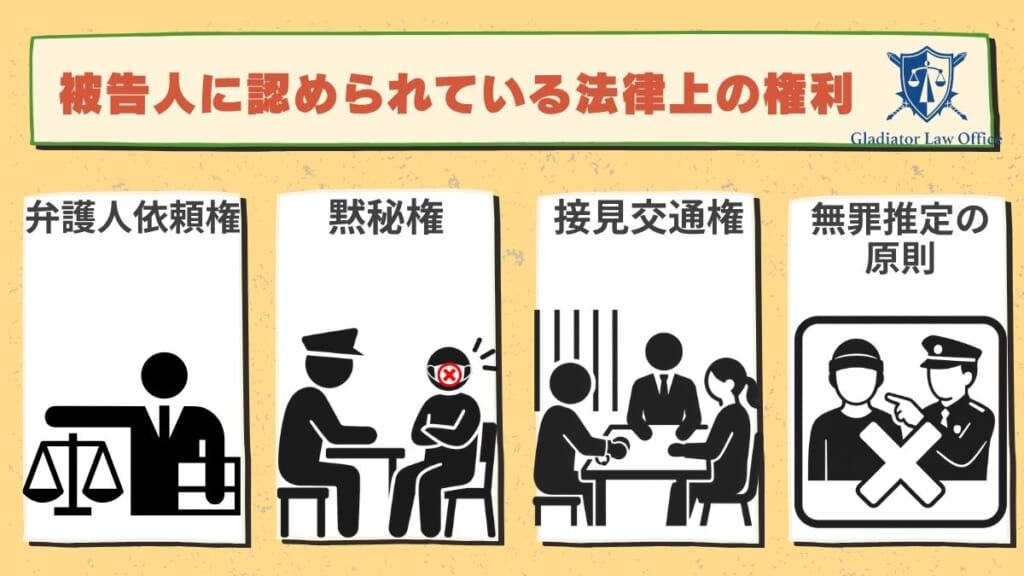
刑事裁判は、国家権力が個人を処罰する重大な手続であるため、誤った判断を防ぎ、公正な裁判を実現するために、被告人にはいくつかの重要な権利が法律で認められています。以下では、法律上被告人に認められている代表的な権利を紹介します。
弁護人依頼権
被告人は、自らを守るために弁護人(弁護士)を依頼する権利を持っています(憲法37条3項、刑事訴訟法30条)。経済的に余裕がない場合には国選弁護制度を利用でき、起訴後は必ず弁護人が付けられる仕組みになっています。
黙秘権
被告人は、自己に不利益な供述を強要されない「黙秘権」を保障されています(憲法38条1項)。この権利により、取り調べや裁判で不利な供述を無理にする必要はなく、あくまで自分の意思で供述することが可能です。
接見交通権
被告人は、弁護人や家族と自由に面会し、やり取りできる「接見交通権」を持ちます(憲法34条、刑事訴訟法39条)。勾留中であっても弁護人とは秘密を守りながら打ち合わせができるため、防御権を実効的に行使できます。
無罪推定の原則
刑事裁判においては「有罪が確定するまでは無罪と推定される」という「無罪推定の原則」が適用されます(憲法31条、刑事訴訟法336条)。つまり、検察官が有罪を立証できない限り、被告人を「犯人」として扱ってはなりません。
被告人に課されている法律上の義務
被告人は、人権保障のもとに裁判を受ける立場ですが、同時に裁判手続を円滑かつ公正に進めるための義務も負っています。これらの義務を守らなければ、裁判が中断したり、不利益を受けたりする可能性があるため注意が必要です。
出頭義務
被告人は、裁判所から指定された期日に必ず出頭しなければなりません(刑事訴訟法60条など)。正当な理由なく欠席すると、裁判所が勾引(強制的に連行する手続)を命じたり、保釈中であれば保釈が取り消されたりすることもあります。
在廷義務
公判期日に出頭した被告人は、判決の言い渡しまで法廷に在席する義務があります(刑事訴訟法285条)。被告人が勝手に退廷した場合でも裁判は進行しますが、その態度は量刑判断に影響を与える可能性があり、極めて不利に働くことがあります。
保釈時の行動制限
起訴後に保釈が認められた場合、被告人には一定の行動制限が課されます。
たとえば、証人や共犯者への接触禁止、裁判所の許可なく住居を変更しない義務などです(刑事訴訟法96条)。これらを違反すると、保釈保証金が没取されたり、再び身柄を拘束されたりする可能性があります。
被告人になった後の刑事裁判の流れ

被告人となった後は、刑事裁判の正式な手続が進んでいきます。刑事裁判は、検察官が犯罪の立証をし、裁判官が判断を下すという厳格な流れに沿って行われます。以下では、起訴から判決までの大まかな流れを確認しておきましょう。
起訴
検察官が「裁判で有罪を立証できる」と判断した場合、被疑者を正式に起訴します。起訴の瞬間から、立場は「被疑者」から「被告人」へ変わります。
起訴には「公判請求」「略式命令請求」の2種類があり、公判請求をされると公開の法廷で裁判が開かれます。
公判期日の指定
起訴後、裁判所は、最初の公判期日を指定し、被告人や弁護人に通知します。
公判期日とは、裁判を行う具体的な日程のことです。刑事裁判は公開の法廷で行われるため、誰でも傍聴することができます。
公判手続き
公判では、検察官による起訴状の朗読から始まり、証拠調べや証人尋問などを経て、弁護人による反論や被告人質問が行われます。裁判所はこれらを通じて事実関係を明らかにし、有罪か無罪かを判断します。刑事裁判の中核部分といえる段階です。
判決
すべての審理が終わると、裁判所は判決を言い渡します。
有罪の場合には刑罰(拘禁刑・罰金など)が科され、執行猶予が付くかどうかもここで決まります。無罪の場合には被告人は直ちに釈放されます。
なお、判決に不服がある場合、控訴や上告といった不服申立ても可能です。
起訴された被告人は保釈請求が可能

被疑者段階で身柄拘束されている場合、被告人となった後も身柄拘束が継続します。しかし、刑事裁判は複数回の公判を経て判決までに時間がかかることが多いため、その間ずっと身柄拘束されると被告人や家族の生活に大きな影響を及ぼします。そこで設けられているのが「保釈制度」です。
保釈請求ができるタイミング
保釈請求は、起訴後に限って認められる手続です。捜査段階(被疑者の段階)では原則として保釈はありませんが、起訴され被告人となった時点で、裁判所に保釈を請求できます。
保釈が許可されれば、一時的に身柄拘束が解かれて、裁判終了まで通常の社会生活を送ることができるようになります。
保釈には保釈保証金が必要
保釈が認められた場合、裁判所に「保釈保証金」を納める必要があります。これは、被告人が裁判に出頭することを担保するための金銭であり、無事に裁判が終了すれば原則返還されます。
保釈保証金の金額は、事件の内容や被告人の資力によって裁判所が決定し、150万円~300万円程度が一般的な相場です。
保釈中の義務
保釈された被告人には、一定の行動制限が課されます。たとえば、証人や共犯者との接触禁止、住居変更時の裁判所への報告義務などです。これらを違反すれば保釈は取り消され、保証金も没収される可能性があります。
犯罪の嫌疑をかけられたときはすぐにグラディアトル法律事務所に相談を
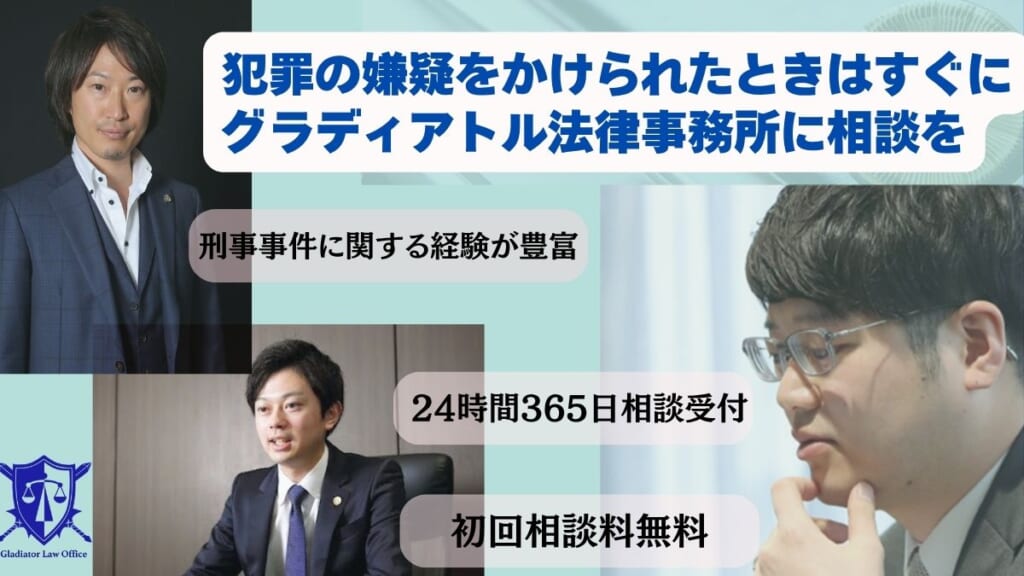
刑事事件は、人生を大きく左右する重大な出来事です。逮捕・勾留されれば自由が奪われ、仕事や家庭にも深刻な影響が及びます。さらに起訴され「被告人」となれば、長期間にわたり裁判に臨むことになり、結果次第では前科や刑罰という重い負担を背負うことになりかねません。このような局面では、一刻も早く刑事弁護に強い弁護士へ相談することが極めて重要です。
グラディアトル法律事務所は、刑事事件に精通した弁護士が多数在籍し、スピーディーかつ戦略的な弁護活動を展開しています。逮捕直後の段階から接見に駆けつけ、取り調べ対応を助言するほか、勾留阻止や早期釈放を目指して行動します。起訴後は、迅速な保釈請求や裁判での無罪主張、量刑の軽減を目指してサポートします。
刑事事件では初動が肝心です。早い段階で弁護士に依頼することで、捜査機関の不当な追及から身を守り、有利な展開を引き寄せることができます。万が一、あなた自身やご家族が犯罪の嫌疑をかけられた場合には、迷わずグラディアトル法律事務所へご相談ください。経験豊富な弁護士が全力で権利を守り、将来を取り戻すために尽力いたします。
まとめ
被告人とは、起訴されて刑事裁判にかけられている人を指し、被疑者や容疑者、民事裁判の被告とは明確に区別されます。被告人には弁護人依頼権や黙秘権といった権利が保障される一方で、出頭義務などの責任も課されています。
刑事裁判は人生を左右する重大な手続であり、適切な対応が不可欠です。犯罪の嫌疑をかけられたときは、刑事事件に強いグラディアトル法律事務所へ早急にご相談ください。