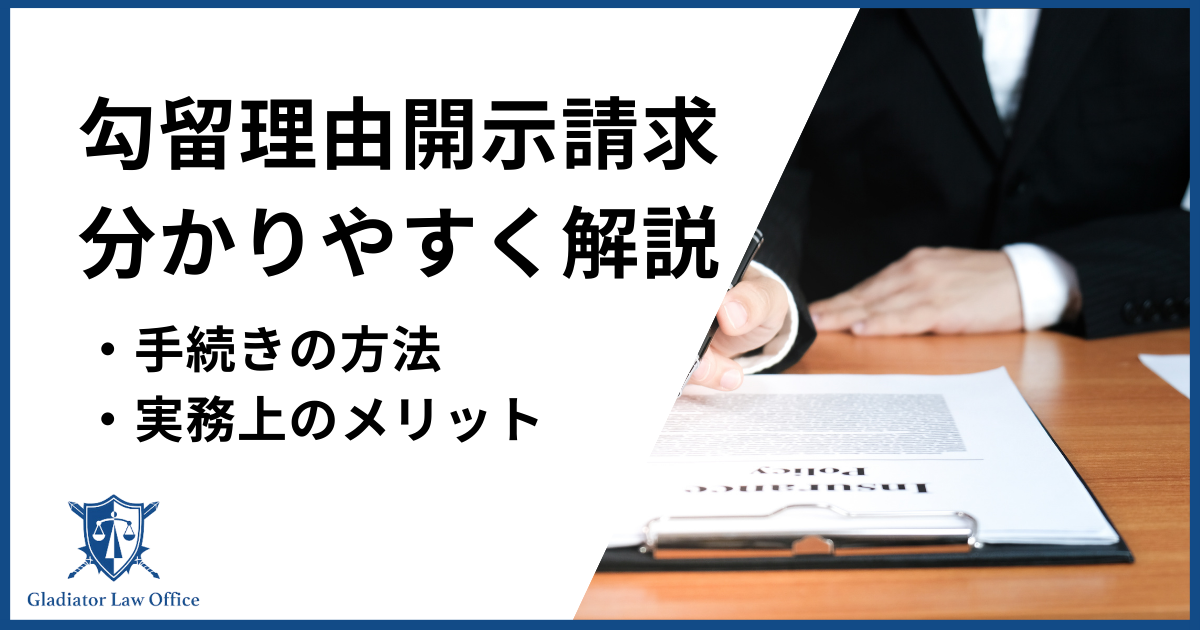「なぜ身柄を拘束されているのか、その理由を知りたい…」
「接見禁止で会うこともできないのを、なんとかしたい…」
こんな状況に置かれている方が使えるのが、勾留理由開示請求という手続きです。
勾留理由開示請求をすれば、身柄拘束の理由を公開の法廷で説明してもらうことができます。ただ、「理由開示」とはいっても、具体的な理由が分かるわけではなく、告げられるのは形式的な内容であるケースがほとんどです。
そこで実務上は、接見禁止中のご家族と対面する、あるいは刑事裁判で有利になる証拠を残す、などの目的でも使われています。
本記事では、勾留理由開示請求の仕組みから、実際の手続きの流れ、4つの実務上のメリット、よくある質問まで、弁護士の視点から解説します。
目次
勾留理由開示請求とは
勾留理由開示請求とは、「なぜ身柄を拘束しているのか」を公開の法廷で説明してもらう手続です。
憲法34条で保障された権利であり、被疑者本人やその家族などが請求できます。
【憲法第三十四条】
何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
具体的な理由が分かるケースは少ない
勾留理由開示請求をすると、勾留理由が開示されますが、具体的な理由が開示されるわけではありません。基本的には、以下のような「刑事訴訟法60条の理由」がそのまま告げられるケースがほとんどです。
・ 被告人が定まった住居を有しない
・ 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある
・ 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由がある
公判で弁護人から強く求めていくと、多少詳しい内容が説明される場合もありますが、「回答する必要はありません」などと取り合ってもらえないケースも多いです。
そこで実務上は、「必ず公開の法廷で行われる」という仕組みを利用して、接見禁止中の当事者と家族の顔合わせや、被疑者の意見陳述を調書として残しておく、などの目的で利用されています。
こういった、勾留理由開示請求の(実際上の)効果は、2章で詳しく紹介します。
勾留理由開示請求をできるのは一度だけ
勾留理由開示請求ができるのは、一度の勾留中に一度だけです。仮に勾留延長されても、2回目の請求はできません。
「勾留理由開示の請求は、第一勾留については勾留の開始せられた当該裁判所において一回に限り許されるものと解すべきである」
(引用:最高裁昭和29年8月5日)
そのため、勾留理由開示請求をする当事者・その家族としては、
・ 勾留理由開示請求ができるチャンスは一度であること
・ 理由開示の他にも、次章で説明するような実際上の効果が大きいこと
などに留意しつつ、どのタイミングで請求するかをしっかり検討する必要があります。
勾留理由開示請求をする実際上のメリット4つ
前章で説明したとおり、勾留理由開示請求で開示される理由自体は、簡単なものです。
もちろん、弁護人としては、裁判官に対して粘り強く釈明を求めていきますが、なかには「回答する必要はありません」などとされて、詳細が開示されないケースもあります。
そこで前述したとおり、実務上は「身柄拘束の理由を教えてもらい、釈放に活用する」という本来的な効用のほかに、以下のような目的でも勾留理由開示請求をすることがあります。
以下で、実際上のメリットを4つ紹介します。

接見禁止中でも、家族と対面できる
勾留理由開示請求は、必ず公開の法廷で実施されます。これは憲法で保障されている権利なので、接見禁止命令の影響をうけません。
そのため、接見禁止中の被疑者でも、開示請求を行えば家族と対面できるというメリットがあります。
■刑事訴訟法
第八十三条
勾留の理由の開示は、公開の法廷でこれをしなければならない。
被疑者にとっても、傍聴席にいる家族の姿を確認できれば、「自分は一人ではない」「家族が見守ってくれている」という支えになるでしょう。
ただし、直接の会話はできません。あくまでも傍聴席から対面できるのみで、直接声をかけることは禁止されています。
法廷で励ましのメッセージを伝えられる
勾留理由の開示公判では、家族も法廷での意見陳述が認められます。
そのため、この陳述の機会を使えば、被疑者に対して間接的に励ましのメッセージを伝えることができます。
被疑者が返事をすることはできませんが、家族の声を聞くだけで勇気づけられるでしょう。
また、ここで家族が陳述した内容は、調書として証拠化されます。
このタイミングで、「再犯防止に向けて監督する意思があること」などを裁判所に伝えておけば、不起訴・執行猶予付き判決などの獲得に向けた効果も期待できます。
捜査機関の取調べが一時的に中断される
開示の公判期日は、被疑者本人が裁判所へ出頭します。検察の取調べも実施されないため、取調べが中断されるというメリットがあります。
たとえ半日でも取調べから解放される時間は、精神的にも大きな効果があるでしょう。
また、開示公判で取調べの状況を陳述すれば、その内容が調書に記載されます。
もしも、違法・不当な取調べが行われていれば、それに対する陳述を調書として残せるので、捜査機関に対する牽制効果も期待できます。
開示公判での意見陳述が調書として残される
開示公判での意見陳述は、すべて調書として記録されます。
このタイミングで、被疑者の供述を証拠化しておけば、その後の取調べで事実に反する自白をしてしまった場合でも、自白の任意性を争いやすくなります。
その他、ここで陳述した内容は、準抗告や勾留取消請求、保釈請求などでも考慮されます。
勾留理由開示請求手続きの流れ
次に、勾留理由開示請求の流れを見ていきます。

①勾留理由開示請求書を提出する
勾留理由開示請求は、必ず書面で行う必要があります。
■刑事訴訟規則
(勾留の理由開示の請求の方式・法第八十二条)
第八十一条 勾留の理由の開示の請求は、請求をする者ごとに、各別の書面で、これ
をしなければならない。
勾留理由開示請求書には、対象事件・被告人などを特定して記載します。質問事項を記載する必要はありません。
ただ、併せて求釈明書を求められるケースが多いので、詳細な質問事項はそちらに記載することになります。
②開示期日が決まる(請求日から5日以内で指定)
開示請求後、開示期日が決まります。
開示公判の日程は、原則として「請求日から5日以内」です。月曜日に請求しない限り、休日を挟むことになるため、日程調整の余地はほとんどありません。
■刑事訴訟規則
(開示の請求と開示期日)
第八十四条 勾留の理由の開示をすべき期日とその請求があつた日との間には、五日
以上を置くことはできない。但し、やむを得ない事情があるときは、この限りでな
い。
③公判当日、勾留理由が開示される

公判当日は、被疑者の人定質問が行われた後、裁判所によって勾留理由が説明されます。
ただ、ここでは形式的な内容しか告げられないため、通常は、弁護人から裁判所への求釈明を行っていきます。
その後、被疑者や弁護人、検察官、請求者(家族など)がそれぞれ意見陳述を行います。
被疑者や家族の意見陳述の方法は、通常の公判期日と大きく変わりません。書面を読み上げるケースもありますし、弁護人とのやり取りによって陳述するケースもあります。
なお、意見陳述の時間は、被疑者・弁護人・検察官・その他請求者がそれぞれ10分以内です。陳述を補うために、書面を差し出すこともできます。
(開示期日における意見陳述の時間の制限等・法第八十四条)
第八十五条の三 法第八十四条第二項本文に掲げる者が開示期日において意見を述べ
る時間は、各十分を超えることができない。
2 前項の者は、その意見の陳述に代え又はこれを補うため、書面を差し出すことが
できる。
勾留理由開示請求は弁護人以外でもできる?
勾留理由開示請求は、法律上、本人・弁護人・配偶者・直系親族・兄弟姉妹などであれば、誰でも行えます。
ただ、弁護人以外が単独で請求することは推奨できません。
なぜなら、勾留理由開示請求の本来的な目的は、あくまでも裁判所に身柄拘束の理由を示してもらい、それを身柄解放に活かすことだからです。
そのためには、単に書面で請求するのではなく、公判期日において、粘り強く釈明を求めていく必要があります。そして、裁判官の説明に不合理な点があれば、それを準抗告や勾留取消請求など、身体拘束からの解放に活かすことも必要でしょう。
弁護人から厳しく追求していくからこそ、勾留理由開示請求の本来的なメリットが期待できるのです。
さらに、前述したとおり、勾留理由開示請求ができるのは一度のみです。
一度しかないチャンスだからこそ、弁護人ともよく相談した上で、最適なタイミングで活用することをおすすめします。
勾留理由開示請求についてよくある質問
実際に多く寄せられる質問について、Q&A形式でお答えします。
起訴後でも請求できますか?
はい。刑事訴訟法82条は「勾留されている被告人は、裁判所に勾留の理由の開示を請求することができる」と規定しており、そもそも起訴後が想定されています。
第八十二条
勾留されている被告人は、裁判所に勾留の理由の開示を請求することができる。
ただし、本記事で説明したような実際上のメリットは、起訴前だからこそ享受できるものです。実務上も起訴前の段階、つまり被告人勾留ではなく、被疑者勾留の段階で行われるケースがほとんどです。
勾留理由を開示するデメリットはありますか?
公開の法廷で行われることが、デメリットにもなり得ます。
家族に限らず誰でも傍聴できるため、被疑者のプライバシーが侵害されるおそれがあるからです。特に、性犯罪などの場合は、被疑者の名前が公になるデメリットのほうが大きいケースもあるでしょう。
勾留理由開示請求をするかは、メリット・デメリットを比較して、弁護人とよく相談して判断しましょう。
勾留理由開示請求をすれば、接見禁止中の家族に会えますか?
「会う」というよりは、傍聴席から「顔を合わせる」という表現が適切です。
法廷で目を合わせたり、意見陳述によってメッセージを伝えたりすることはできますが、直接会話することはできません。あくまでも傍聴席からの対面に限られます。
本当に会って話がしたい場合は、接見禁止を解除するための手続きも並行して検討するべきでしょう。
勾留理由開示請求を考えている方はグラディアトル法律事務所へご相談ください。
ご家族が逮捕・勾留され、勾留理由開示請求を検討している方は、ぜひグラディアトル法律事務所にご相談ください。
本記事で説明したとおり、勾留理由開示請求によるメリットを最大限に享受するには、公判での求釈明、意見陳述の内容、その後の準抗告や保釈請求への活用など、高度な刑事弁護の技術が必要です。
グラディアトル法律事務所の弁護士は数多くの刑事事件を取り扱っており、接見禁止の解除、不起訴処分の獲得、早期の身柄解放など、豊富な解決実績を有しています。
「勾留理由開示請求をすべきか迷っている」「いつ請求するのがベストか」「接見禁止で家族に会えない」など、どんなお悩みでも構いません。24時間365日相談を受け付けていますので、お気軽にご相談ください。
まとめ
最後に、この記事のポイントをまとめます。
◉勾留理由開示請求の基本
勾留理由開示請求とは?
→裁判所に「なぜ身柄を拘束しているのか」を公開の法廷で説明してもらう手続き。憲法34条で保障された権利。
開示される内容は?
→「証拠隠滅のおそれ」など形式的な説明のみ。詳しい理由は開示されないことがほとんど。
請求できる回数は?
→一度の勾留につき一回限り。勾留延長されても再度の請求は不可。
◉実際上のメリット4つ
①接見禁止中でも法廷で家族と対面できる
②取調べが一時的に中断される
③法廷で励ましのメッセージを伝えられる
④意見陳述が調書として残り、後の手続きで活用できる
◉手続きの流れ
①勾留理由開示請求書を提出
②開示期日が決まる(請求から5日以内)
③公判で勾留理由が開示される(所要時間30分程度)
◉注意すべきポイント
誰が請求できる?
→被疑者本人、弁護人、家族など。ただし弁護人と連携することが重要。
デメリットは?
→公開法廷のため、プライバシーが侵害されるおそれがある。
以上です。
刑事裁判でお困りの方は、ぜひグラディアトル法律事務所にご相談ください。
グラディアトル法律事務所の弁護士は数多くの刑事事件を取り扱っており、圧倒的なノウハウと実績を有しています。
それぞれの弁護士が得意分野をもっておりますので、各事件の特性に応じた充実した刑事弁護をご提供いたします。