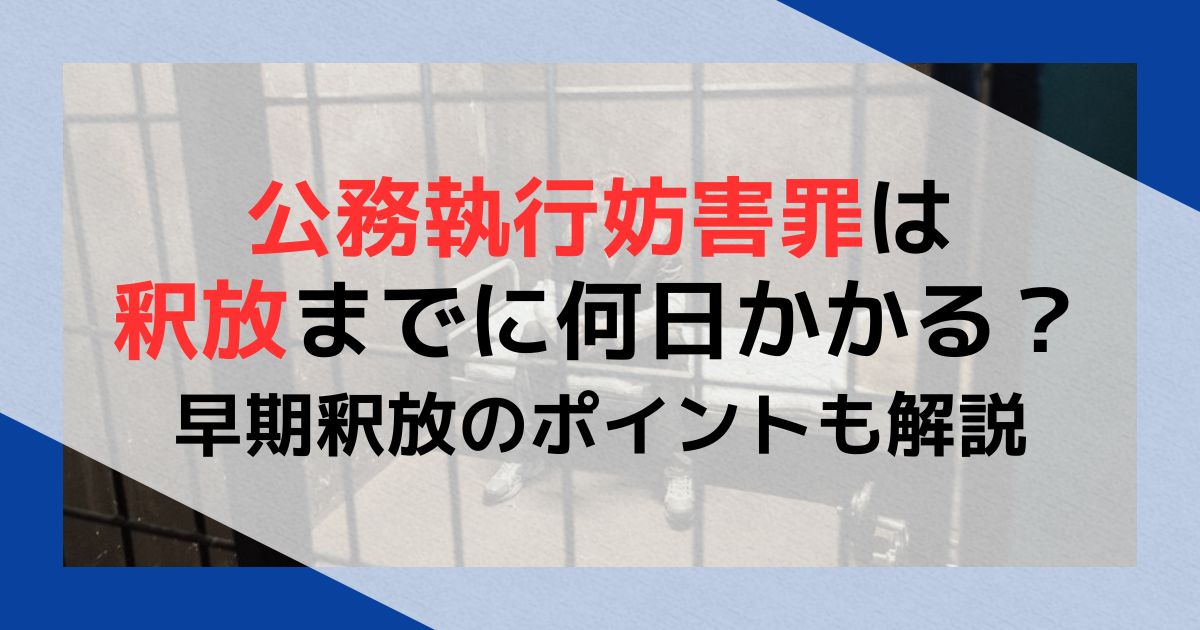「公務執行妨害で逮捕された家族がいつ釈放されるのか心配…」
「早期釈放のためにできることはないのか」
公務執行妨害罪は比較的逮捕率が高い犯罪です。
逮捕されたあとは長期間にわたって身柄拘束を受ける可能性があるため、早期釈放に向けて迅速に対応していく必要があります。
そのなかで、釈放までにどの程度の期間を要するのか、釈放のチャンスはどこにあるのかなど、基本的な知識を身につけておくことは非常に重要です。
そこで本記事では、公務執行妨害罪で釈放までにかかる期間や釈放のタイミングなどを解説します。
釈放までの期間が長引きやすいケースや、早期釈放につながる行動なども詳しくまとめているので、ぜひ最後まで目を通してみてください。
※刑法改正により、2025年6月から懲役刑と禁錮刑は「拘禁刑」に一本化されています。
| 【拘禁刑とは?】 犯罪者を刑事施設に収容し、改善更生に必要な作業を命じたり、指導したりする刑罰のこと。刑務作業は義務ではなく、受刑者の特性に応じた支援プログラムが提供される。 |
目次
公務執行妨害罪は釈放までに何日かかる?逮捕後の基本的な流れ
まずは、公務執行妨害罪で逮捕されたあとの流れを解説します。
各段階でどの程度の期間を要するのかが把握できれば、釈放までの日数もイメージできるようになるはずです。
警察の取り調べ・送致|最大48時間
公務執行妨害罪で逮捕されると、最大48時間の間、警察署で取り調べを受けます。
取調室のなかで警察官と対面し、事件当時の状況や犯行に至った動機などを詳しく聞かれることになるでしょう。
取り調べ中は外部との連絡が制限され、基本的に弁護士以外との面会は認められません。
警察が取り調べを終えると、ほとんどのケースで検察への送致が決定し、身柄と捜査資料が引き継がれることになります。
検察の取り調べ|最大24時間
公務執行妨害罪で送致されると、今度は検察官による取り調べを受けなければなりません。
検察官は警察の捜査資料を踏まえて、再度、事実関係の確認や証拠の精査、被疑者への聴取を実施し、24時間以内に勾留を請求するか、被疑者を釈放するかを決定します。
とはいえ、24時間以内に釈放を認められるほどの捜査が進むことはほとんどなく、勾留請求されるケースが一般的です。
なお、検察官は裁判官に対して勾留請求しますが、却下されることは基本的にありません。
勾留|最大10日間
勾留が決定すると、被疑者は原則として10日間の身柄拘束を受けます。
そして、引き続き、検察官による捜査や取り調べが実施されることになります。
勾留中は、原則として家族や知人との面会も可能です。
とはいえ、勾留が決定した時点でしばらくは家に帰れず、仕事も休むことになるため、日常生活への影響は計り知れません。
勾留延長|最大10日間
通常の勾留期間では捜査が十分に進まない場合など、やむを得ない事由があるときは、勾留延長がおこなわれます。
延長される期間は、最大10日間です。
つまり、通常の勾留期間10日間と通算すると、最大で20日間にわたる身柄拘束を受ける可能性があります。
なお、2023年における公務執行妨害罪での勾留期間・許可人員は以下のとおりです。
| 勾留期間 | 5日以内 | 10日以内 | 15日以内 | 20日以内 |
| 許可人員 | 31 | 367 | 42 | 452 |
(参照:検察統計調査|法務省)
起訴・不起訴の決定
公務執行妨害罪で勾留されている間に、起訴または不起訴が決定されます。
不起訴になれば、その時点で釈放され、元の生活に戻ることが可能です。
起訴されると裁判に移行し、有罪になると刑罰が言い渡されます。
公務執行妨害罪の刑罰は「3年以下の懲役もしくは禁錮(拘禁刑)または50万円以下の罰金」です。
なお、公務執行妨害罪では、略式起訴が選択されるケースも少なくありません。
略式起訴とは、公開の裁判を省略し、書面審理のみで罰金刑を確定する手続きのことです。
実際、2023年の調査では半数以上の事件で、略式起訴が選択されています。(参考:検察統計調査|法務省)
関連コラム:公務執行妨害罪は懲役になる?執行猶予率や初犯の量刑相場を解説
公務執行妨害罪で逮捕後に釈放されるタイミングと釈放率
次に、公務執行妨害罪で逮捕後に釈放されるタイミングと釈放率を解説します。
送致が不要と判断されたとき
公務執行妨害罪で逮捕された場合、釈放される最初のタイミングは送致が不要と判断されたときです。
軽微な犯罪であり、被害者も反省しているようなケースでは、警察が「送致するほどの事件ではない」と判断し、微罪処分とすることがあります。
微罪処分になれば、その時点で刑事手続きが終了し、被疑者の身柄も解放されます。
なお、2023年の統計によると、犯罪全体の微罪処分率は26.4%です。(参照:令和6年版犯罪白書|法務省)
勾留請求が見送られたとき
送致後に釈放される最近のタイミングは、勾留請求が見送られたときです。
検察官が身柄拘束を続ける必要がないと判断し、勾留請求を見送ると、被疑者は釈放されます。
ただし、刑事事件においては、勾留請求によって引き続き身柄拘束を受けるケースがほとんどです。
実際、2023年に公務執行妨害罪で逮捕された1,277件のうち、1,038件で勾留請求がなされており、勾留請求率は約8割に及びます。(参照:検察統計調査|法務省)
勾留請求が却下されたとき
勾留請求が却下されたときも、釈放のタイミングです。
勾留請求は検察官から裁判所に対しておこなわれますが、裁判官が必ずしも許可するわけではありません。
被疑者の逃亡・証拠隠滅のおそれがない場合や社会的影響が小さい場合などは、身柄拘束の必要性を認めず、勾留請求を却下することがあります。
そして、勾留を回避した被疑者は、その時点で釈放されるわけです。
2023年では、公務執行妨害罪における勾留請求のうち、許可890件・却下148件となっており、全体の約14%が却下されています。(参照:検察統計調査|法務省)
勾留決定に対する準抗告が認められたとき
逮捕後に釈放されるタイミングのひとつとして「勾留決定に対する準抗告が認められたとき」が挙げられます。
準抗告とは、裁判所が下した勾留決定に対して不服を申し立てる手続きのことです。
身柄拘束の必要性がないことを主張して、裁判所に再審査を求めます。
準抗告が認められると、勾留決定が取り消され、被疑者は速やかに釈放されます。
2023年では、1万5,053件の準抗告が申し立てられ、そのうちの約18%にあたる2,744件で認容されています(出典:令和5年司法統計年報|最高裁判所事務局)。
勾留決定後の勾留取消請求が認められたとき
勾留決定後の勾留取消請求が認められたときも、釈放されるタイミングのひとつです。
身柄拘束の必要性がなくなったことを主張し、裁判所に認めてもらえれば、勾留が取り消され、被疑者は釈放されます。
たとえば、事件の捜査が進展して証拠隠滅・逃亡のおそれがなくなった場合や、家族の監督を得られるようになった場合などは、勾留取消請求を認めてもらえることがあるかもしれません。
2023年においては、全国で1,398件の勾留取消請求がなされ、そのうち128件が認容されています。
(出典:令和5年司法統計年報|最高裁判所事務局)
割合でいうと約9%にとどまるため、勾留取消請求には高いハードルがあるといえるでしょう。
勾留延長請求が却下されたとき
勾留延長請求が却下されたときも、被疑者は釈放されます。
具体的にいうと、通常の勾留期間が満了する際に、検察官が最大10日間の延長を請求したものの、裁判官が必要性を認めず却下した場合です。
ただし、勾留延長請求が却下されるケースはほとんどありません。
2023年の統計によると、公務執行妨害事件における勾留延長請求は494件が許可され、却下されたのはたったの6件です。(参照:検察統計調査|法務省)
不起訴処分になったとき
不起訴処分になれば、その時点で被疑者が罪に問われることはなくなり、身柄も解放されます。
2023年の調査によると、公務執行妨害罪で起訴されたのが766人、不起訴になったのが940人です。
割合でいうと、全体の約55%が不起訴とされています。(参照:検察統計調査|法務省)
なお、不起訴処分となれば前科がつかないので、その後の社会生活への影響も最小限に抑えられるでしょう。
関連コラム:公務執行妨害罪の不起訴率は約55%!不起訴獲得に向けた対処法を解説
処分保留になったとき
公務執行妨害罪で釈放されるタイミングのひとつとして、「処分保留になったとき」も挙げられます。
処分保留とは、検察官が身柄拘束期間中に起訴・不起訴の判断ができず、保留したまま被疑者の身柄を解放する手続きのことです。
なお、処分保留は不起訴とは異なり、釈放されてはいるものの、事件自体が終結したわけではありません。
釈放後に捜査が進み、起訴される可能性も残されています。
起訴後に保釈が決定したとき
身柄が解放される最後の機会となるのが、起訴後の保釈です。
起訴された被告人が裁判所に保釈請求をおこない、許可された場合に、保釈保証金を納付することで身柄が解放されます。
2023年においては、刑事事件全体で起訴された4万1,857人のうち、1万3,129人が保釈されています。
(出典:令和5年司法統計年|最高裁判所事務局)。
なお、保釈中に逃亡・証拠隠滅などの行為に及んだ場合は、再び身柄拘束を受ける可能性があります。
関連コラム:公務執行妨害罪は起訴率45%!起訴されやすいケースや回避方法を解説
公務執行妨害事件で釈放されるためにできる行動
次に、公務執行妨害事件で釈放されるためにできる行動を紹介します。
主に4つのポイントが挙げられるので、一つひとつ詳しくみていきましょう。
反省と謝罪の意思を示す
公務執行妨害で早期釈放を目指すのであれば、反省と謝罪の意思を示すことが重要です。
罪を認めて真摯に反省していることが捜査機関に伝われば、再犯リスクや証拠隠滅・逃亡のおそれが低いと判断され、釈放を認めてもらいやすくなります。
ただし、反省や謝罪の意思を口にするだけでは不十分です。
反省文を提出したり、国・自治体に寄付したり、具体的な行動で示すことが重要です。
身元引受人を立てる
身元引受人を立てれば、釈放される可能性が高くなります。
身元引受人がいることで、「被疑者には適切な監督者がいる」「逃亡や証拠隠滅の恐れが低い」と判断されやすくなるためです。
家族や職場の上司など信頼できる人物が身元引受人となり、身柄引受書を提出した場合は、その日のうちに釈放されるケースもあります。
示談を試みる
公務執行妨害罪で逮捕された場合は、示談ができないかどうか検討してみましょう。
基本的に、公務執行妨害の被害者は国・自治体になるので、示談による解決は難しいです。
しかし、公務員個人にけがを負わせた場合などは、個別に示談できる可能性もあります。
そして、捜査機関に対して示談成立をアピールできれば、早期釈放につながることもあるでしょう。
できるだけ早く弁護士に相談する
公務執行妨害で逮捕された場合は、できるだけ早く弁護士に相談してください。
逮捕直後から弁護士が介入すれば、身柄拘束の長期化を防ぐことが可能です。
たとえば、弁護士は逮捕後すぐに接見し、取り調べ対応のアドバイスをおこないます。
また、捜査機関や裁判所に対しても、身柄拘束の必要性がないことを主張してくれるはずです。
対応が遅れるほど、釈放のチャンスは失われていきます。
早期相談が釈放に向けた最短ルートとなるため、迷わず弁護士に連絡することが重要です。
公務執行妨害事件で釈放までの期間が長引きやすいケース
ここでは、公務執行妨害事件で釈放までの期間が長引きやすいケースを解説します。
自身の状況と照らし合わせながら読み進めてみてください。
否認している場合
加害者が公務執行妨害の容疑を否認している場合は、釈放までの期間が長引く傾向があります。
否認事件では、証拠隠滅や逃亡のおそれがあり、身柄拘束の必要性が高いと判断されやすいからです。
また、警察や検察も入念に捜査を進める必要があるため、結果的に勾留期間が延びやすくなります。
もちろん、冤罪を疑われているのであれば一貫して否認し続けるべきです。
しかし、犯行が事実であるにもかかわらず否認する行為は、無駄に釈放を遅らせるだけなので注意してください。
証拠隠滅のおそれがあると判断された場合
公務執行妨害事件で証拠隠滅のおそれがあると判断された場合は、釈放までの期間が長引きやすくなります。
たとえば、共犯者がいる場合や取り調べで言い逃ればかりしている場合などは、証拠隠滅のリスクを考慮し、釈放してもらえない可能性が高いです。
反対に証拠が出揃っている場合は、そもそも隠滅のリスクが低いので、早い段階での釈放を認めてもらえることがあります。
実刑判決の可能性が高い場合
釈放までの期間が長引きやすいケースのひとつは、実刑判決の可能性が高い場合です。
実刑が見込まれる被疑者を釈放すると、刑罰をおそれて逃亡するリスクがあります。
そのため、身柄拘束されたまま捜査や裁判が進められる傾向にあるのです。
たとえば、過去に同様の前科がある場合や、事件の態様が悪質で被害が重大な場合などは実刑になりやすく、釈放のハードルも高くなります。
身元が安定していない場合
身元が安定していない場合も、釈放までの期間が長引きやすいです。
住所不定、定職がない、身元引受人がいないといった状況では、「逃亡のおそれが高い」と判断されてしまいます。
逆にいえば、家族と生活している場合や、学校・職場とのつながりがある場合などは、釈放が認められやすくなるわけです。
公務執行妨害事件で早期釈放を目指すならグラディアトル法律事務所に相談を!
公務執行妨害事件で早期釈放を目指すなら、グラディアトル法律事務所にご相談ください。
弊所は、公務執行妨害事件をはじめとした刑事事件全般を得意とする法律事務所です。
これまでにも数々の事件に携わり、早期釈放を実現させてきた実績があります。
経験豊富な弁護士が24時間365日体制で相談に応じており、地域を問わず、速やかに弁護活動を実施することが可能です。
初回相談は無料、LINE相談にも対応しています。
依頼者に合わせた無理のない料金を提案させていただくので、まずはお気軽にお問い合わせください。
まとめ
本記事のポイントは以下のとおりです。
- ◆ 公務執行妨害罪で逮捕されると、起訴・不起訴が決まるまで最大23日にわたる身柄拘束を受ける
- ◆ 公務執行妨害罪で逮捕後に釈放されるタイミングは主に9つある
- ◆ 否認している場合や実刑の可能性が高い場合、身元が安定していない場合は釈放までの期間が長引きやすい
- ◆ 早期釈放を目指すなら反省の態度を示し、身元引受人を立てるのが効果的
公務執行妨害罪で逮捕されると、起訴・不起訴が決定するまで、最大23日間にわたる身柄拘束を受けなけれなりません。
家に帰れず、職場や学校に行くこともできないので、釈放までの期間が長引くほど社会生活に復帰するハードルが高くなっていきます。
そのため、家族が逮捕されてしまった場合などは、できるだけ早く弁護士に相談し、弁護活動に着手してもらうことが大切です。
グラディアトル法律事務所では、急を要する案件に即日対応しています。
弊所弁護士が逮捕直後から介入できれば、その日のうちに釈放される可能性もあります。
初回相談は無料なので、少しでも不安に感じることがあるなら、まずは弊所にご相談ください。