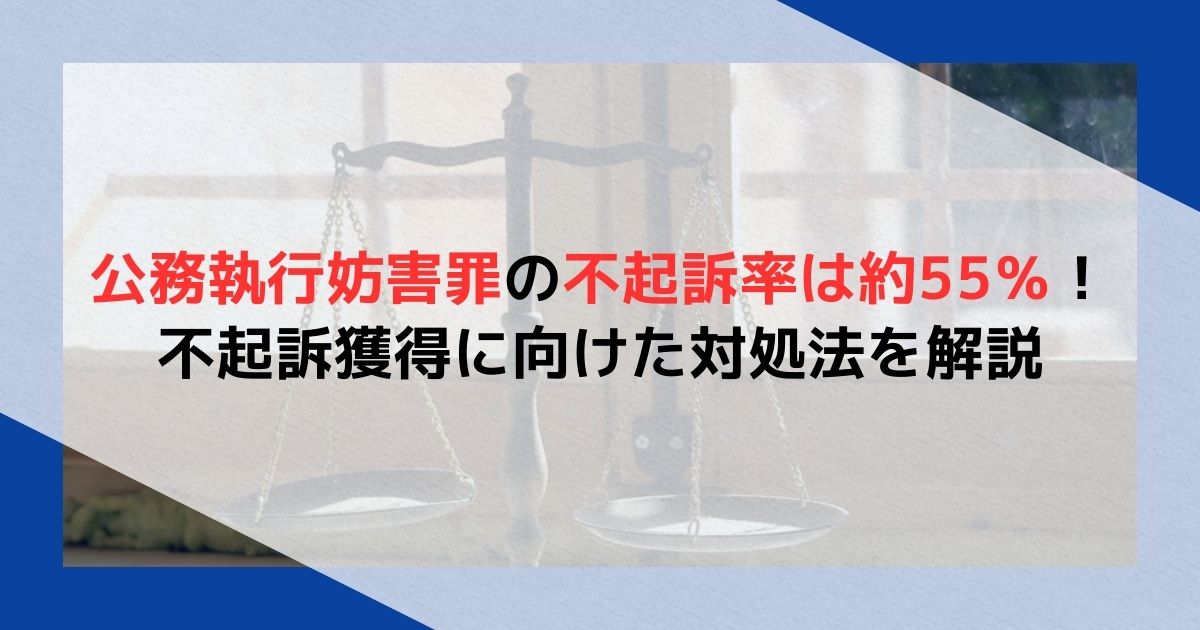「公務執行妨害罪で捕まってしまった…不起訴のなる可能性はどの程度あるのか」
「不起訴を獲得するにはどうすればよいのか」
公務員に暴行・脅迫を加えて公務の執行を妨害した場合は、公務執行妨害罪が成立します。
しかし、不起訴処分を獲得できれば、懲役刑(拘禁刑)などの刑罰を受けず、前科もつかずに、これまでどおりの生活を取り戻すことが可能です。
つまり、起訴になるか不起訴になるかで、その後の人生は大きく変わってくるといっても過言ではありません。
実際、公務執行妨害罪の罪に問われ、なんとかして不起訴処分を獲得できないのか、模索している人も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、公務執行妨害罪の不起訴率や不起訴を獲得するための方法などを解説します。
今後の処遇に少しでも不安を感じている方は、本記事を参考にしてみてください。
※刑法改正により、2025年6月から懲役刑と禁錮刑は「拘禁刑」に一本化されています。
| 【拘禁刑とは?】 犯罪者を刑事施設に収容し、改善更生に必要な作業を命じたり、指導したりする刑罰のこと。刑務作業は義務ではなく、受刑者の特性に応じた支援プログラムが提供される。 |
目次
公務執行妨害罪の不起訴率は約55%
検察庁の統計によると、公務執行妨害罪の不起訴率は約55%です。(参照:検察統計調査|法務省)
2023年に公務執行妨害罪で起訴されたのは766人、不起訴となったのは940人でした。
なお、犯罪全体の不起訴率は68%です。
つまり、公務執行妨害罪は不起訴率が低く、起訴されやすい犯罪であることがわかります。
公務執行妨害罪で不起訴になりやすいケース
次に、公務執行妨害罪で不起訴になりやすいケースをみていきましょう。
自身が置かれている状況と照らし合わせながら読み進めてみてください。
犯行の悪質性が低い場合
公務執行妨害罪で不起訴になりやすいのは、犯行の悪質性が低い場合です。
「犯行の悪質性が低い」とは、以下のようなケースを指します。
- ◆ 暴行・脅迫の程度が軽い
- ◆ 動機に情状酌量の余地がある
- ◆ 犯行が偶発的で計画性がない
たとえば、職務質問してきた警察官の手を払いのけた程度であれば、公務執行妨害罪で検挙されることはあっても、起訴される可能性は比較的低いと考えられます。
一方で、凶器を片手に殴る蹴るの暴行を繰り返した場合などは、犯行の悪質性が高いと判断され、起訴の可能性が高くなります。
初犯の場合
公務執行妨害罪の罪に問われても、初犯の場合は不起訴になりやすい傾向があります。
初犯であれば再犯のリスクが低く、社会的な影響も限定的だと判断されるためです。
もちろん、初犯であっても犯行が悪質な場合や、反省の態度が見られない場合は起訴されることもあります。
あくまでも、個別の事情が総合的に考慮されたうえで、起訴・不起訴が判断されることを理解しておきましょう。
罪を認めて捜査に協力している場合
罪を認めて捜査に協力している場合も、不起訴を獲得しやすくなります。
反省する姿勢は、更生の可能性に直結するものです。
たとえば、反省文を提出したり、取り調べに誠意をもって対応していたりすれば、検察官の心証も良くなり、不起訴となることがあります。
反対に、言い逃れをして横暴な態度を取り続けているような場合は、情状酌量の余地がないと判断され、起訴されやすくなるでしょう。
犯行が事実であっても、その後の言動次第で、起訴・不起訴の判断が変わり得ることを念頭に置いておくようにしてください。
公務執行妨害罪で不起訴を獲得できなかった場合はどうなる?
次に、公務執行妨害罪で不起訴を獲得できなかった場合のリスクについて解説します。
「3年以下の懲役・禁錮(拘禁刑)または50万円以下の罰金」に処される可能性がある
公務執行妨害罪で不起訴を獲得できなかった場合は「3年以下の懲役・禁錮(拘禁刑)または50万円以下の罰金」に処される可能性があります。
起訴後の有罪率は99%以上なので、起訴された時点でほぼ確実に上記の刑罰を言い渡されることになるでしょう。
なお、公務執行妨害罪では略式起訴による罰金刑に処されるケースが多くみられます。
【令和5年における起訴処分の内訳】
| 略式起訴(起訴段階で罰金刑が確定する) | 419人 |
| 正式起訴(裁判で刑罰の内容が決まる) | 347人 |
(参考:検察統計調査|法務省)
一方で、正式起訴で裁判に進んだ場合は、懲役・禁錮(拘禁刑)を言い渡されることが多いです。
令和5年における通常第一審の判決では、懲役・禁錮刑が157人、罰金刑が40人となっています。
懲役・禁錮刑となった157人の科刑状況は以下のとおりです。
(参考:令和6年版犯罪白書|法務省)
公務執行妨害罪では「1年以上2年未満の執行猶予」の刑罰に処されるケースが最も多くなっています。
関連コラム:公務執行妨害罪は懲役になる?執行猶予率や初犯の量刑相場を解説
ほぼ確実に前科がつく
公務執行妨害罪で不起訴を獲得できなかった場合、基本的に前科は避けられません。
公務執行妨害罪で起訴され、有罪判決が確定した時点で、罰金刑や執行猶予付き判決であっても前科が記録されます。
前科がつくと、社会生活に以下のような不利益をもたらします。
- ◆ 就職活動で不利になる
- ◆ 資格・職業の制限を受ける
- ◆ 海外渡航が制限される
- ◆ 解雇・退学になる可能性がある
- ◆ 再犯時の刑事処分が厳しくなる
一度ついた前科が消えることはありません。
刑罰はもちろん、前科を回避するためにも、不起訴処分の獲得に向けては可能な限りの対策を講じる必要があります。
【注意】公務執行妨害罪は示談による不起訴獲得が難しい
公務執行妨害罪は、示談による不起訴獲得が実質的に難しい犯罪といえます。
公務執行妨害罪の被害者は、公務員個人ではなく、国や自治体です。
そのため、示談交渉を持ち掛けたとしても、受け入れてもらえることはほとんどありません。
公務員がけがをした場合など、個別の被害については示談できる余地があるものの、基本的には示談以外の方法で不起訴を目指すことになります。
公務執行妨害罪で不起訴を獲得するためにできること
次に、公務執行妨害罪で不起訴を獲得するためのポイントを解説します。
反省の態度を十分に示す
公務執行妨害罪で不起訴を獲得するためには、反省の態度を示すことが重要です。
加害者本人に反省の態度が見られる場合は、再犯リスクが低く、更生の可能性が高いと判断されやすくなります。
具体的には、罪を素直に認める、弁護士を通じて反省文を提出するなどの行動が挙げられるでしょう。
また、取り調べに誠意をもって臨むことも、反省している姿勢を伝えるためには欠かせないポイントといえます。
冤罪を疑われた場合は否認し続ける
公務執行妨害の冤罪を疑われた場合は、一貫して否認し続けるようにしてください。
一度でも罪を認めるような発言をしてしまうと、取消すことが難しくなります。
実際、公務執行妨害罪は成立するかどうかの判断が難しいケースも少なくありません。
たとえば、意図せず手が当たってしまった場合は「故意」がないため、公務執行妨害罪の成立を否定できます。
また、公務員の職務が適法ではなかった場合も、公務執行妨害罪は成立しません。
取り調べでは、やってもいない罪を認めるように誘導尋問される可能性もゼロではないので、弁護士とも相談しながら、事実を伝えていくことが大切です。
刑事事件が得意な弁護士に相談する
公務執行妨害罪で検挙された場合は、できるだけ早く、刑事事件が得意な弁護士に相談しましょう。
経験豊富な弁護士に相談すれば、個々のケースに応じた最善の対応策を提案してくれるはずです。
具体的には、不起訴の獲得に向けて以下のようなサポートをおこなってくれます。
弁護士に相談・依頼するにはそれなりの費用を要しますが、刑罰に処されたり、前科がついたりすることに比べると大した問題にはならないはずです。
手遅れになる前に、頼れる弁護士を見つけて相談することが大切です。
公務執行妨害罪の罪に問われたときはグラディアトル法律事務所に相談を!
本記事のポイントは以下のとおりです。
- ◆ 公務執行妨害罪の不起訴率は約55%
- ◆ 犯行の悪質性が低い場合や初犯の場合などは不起訴になりやすい
- ◆ 不起訴を獲得できなければ「3年以下の懲役・禁錮(拘禁刑)または50万円以下の罰金」に処され、前科がつくおそれがある
- ◆ 公務執行妨害罪で不起訴を獲得するのは反省の態度を示すことが重要
公務執行妨害罪で不起訴を獲得するためには、専門的な知識と経験が求められます。
一人で悩んでいても事態は好転しないので、一刻も早く弁護士に相談することが重要です。
グラディアトル法律事務所では、経験豊富な弁護士が24時間・365日体制で相談を受け付けています。
家族が逮捕された場合や、警察から電話がかかってきた場合など、急を要する事態にも対応可能です。
初回相談は無料、LINEでの相談にも応じているので、困ったときはいつでもお問い合わせください。