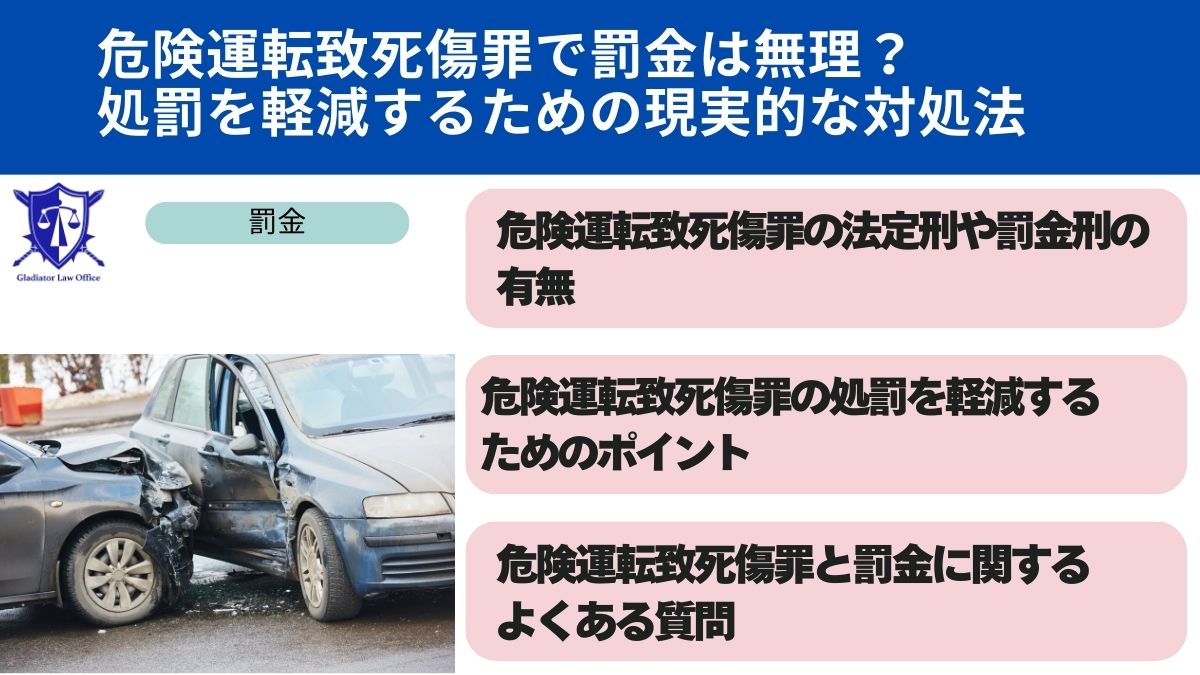「危険運転致死傷罪に問われた場合、罰金刑で済ませることはできる?」
「危険運転致死傷罪の処罰を軽減する方法を知りたい」
「危険運転から過失運転に変わったときは罰金刑になる?」
危険運転致死傷罪は、飲酒運転やあおり運転など、悪質な運転によって他人にけがをさせたり死亡させたりした場合に適用される、非常に重い犯罪です。危険運転致死傷罪を犯してしまった方の中には、「罰金刑で済ませることはできないのか」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。
しかし、結論からいえば、危険運転致死傷罪には罰金刑の規定がなく、処罰は原則として懲役(拘禁刑)一択です。
それでも、事故の状況や被害者との関係、刑事処分の流れによっては、より軽い処罰や不起訴処分となる可能性もゼロではありません。
本記事では、
| ・危険運転致死傷罪の法定刑や罰金刑の有無 ・危険運転致死傷罪の処罰を軽減するためのポイント ・危険運転致死傷罪と罰金に関するよくある質問 |
などについてわかりやすく解説します。
今まさに対応を迫られている方や、ご家族が逮捕された方にとって、今後の判断材料となる内容をまとめていますので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
危険運転致死傷罪の法定刑|罰金刑はないため懲役(拘禁刑)一択
危険運転致死傷罪は、極めて悪質な運転行為によって人を死傷させた場合に適用される重大な犯罪です。この罪には罰金刑の規定がなく、起訴され有罪となった場合は、原則として懲役(拘禁刑)による処罰が科されます。以下では、自動車運転処罰法に規定される危険運転致死傷罪の類型ごとに、具体的な法定刑を確認していきましょう。
自動車運転処罰法2条の危険運転致死傷罪の法定刑
自動車運転処罰法2条は、以下のような故意に近い悪質な運転態様によって人を死傷させた場合に適用されます。
| ・アルコールや薬物の影響で正常な運転が困難な状態での運転 |
| ・制御困難な高速度での走行 |
| ・信号無視や蛇行運転などによる著しい交通規則違反 |
| ・他車を妨害する目的の運転(いわゆる「あおり運転」) |
これらの運転で事故を起こした場合の法定刑は、以下のとおりです。
| ・被害者を負傷させた場合……15年以下の懲役(拘禁刑) ・被害者を死亡させた場合……1年以上の有期懲役(拘禁刑) |
このように非常に重い刑罰が規定されていることからも、2条の危険運転がいかに重大な違法行為とみなされているかがわかります。
自動車運転処罰3条の危険運転致死傷罪の法定刑
自動車運転処罰法第3条は、アルコールや薬物の影響により正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で運転し、その影響で正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた場合に適用されます。
2条の行為類型が故意に近い悪質なものであるのに対して、3条の行為類型は過失に近いものであるため、2条よりも法定刑が軽くなっています。
| ・被害者を負傷させた場合……12年以下の懲役(拘禁刑) ・被害者を死亡させた場合……15年以下の懲役(拘禁刑) |
それでも法定刑は、懲役(拘禁刑)のみですので、危険運転致死傷罪に問われた場合は、罰金刑が適用される余地はありません。
罰金で済ませるには危険運転致死傷罪の成立を争う
危険運転致死傷罪が成立すると、有罪の場合は必ず懲役(拘禁刑)となり、罰金で済ませることはできません。そのため、もし罰金刑の可能性を残したいのであれば、危険運転致死傷罪が成立しないことを主張し、より軽い「過失運転致死傷罪」の適用を目指すことが重要です。
危険運転致死傷罪と過失運転致死傷罪の違い
危険運転致死傷罪と過失運転致死傷罪は、どちらも交通事故によって人を死傷させたという点で共通しますが、その行為態様に大きな違いがあります。
| 危険運転致死傷罪 | 過失運転致死傷罪 | |
|---|---|---|
| 行為態様 | 故意に近い危険な運転による事故 | 不注意による事故 |
| 具体例 | 飲酒・薬物・あおり運転など | わき見運転、操作ミスなど |
| 法定刑 | 拘禁刑のみ(罰金刑なし) | 拘禁刑または罰金刑 |
危険運転致死傷罪が成立するには、単なる運転ミスではなく、極めて危険な運転であったことが必要です。
この点を争っていくことで、「危険運転ではなく過失による事故にすぎない」と判断されれば、過失運転致死傷罪が適用される可能性が出てきます。
過失運転致死傷罪が適用されれば罰金刑の可能性も
過失運転致死傷罪は、自動車の運転者が必要な注意を怠り、人を死傷させた場合に適用される犯罪です。法定刑は、7年以下の懲役・禁錮(拘禁刑)または100万円以下の罰金と定められていますので、危険運転致死傷罪とは異なり罰金刑の選択肢があります。
実際には、軽傷かつ初犯であること、被害者との示談が成立していることなどを理由に、起訴猶予や罰金刑で済むケースが多くあります。
したがって、危険運転致死傷罪の疑いをかけられたときの弁護方針としては、
| ・事故当時の状況や運転態様から危険運転致死傷罪に該当しないことを主張する ・単なる過失であると認定されるように証拠を揃える |
というアプローチが必要になります。
危険運転致死傷罪による処罰を軽減するためにできる3つのこと
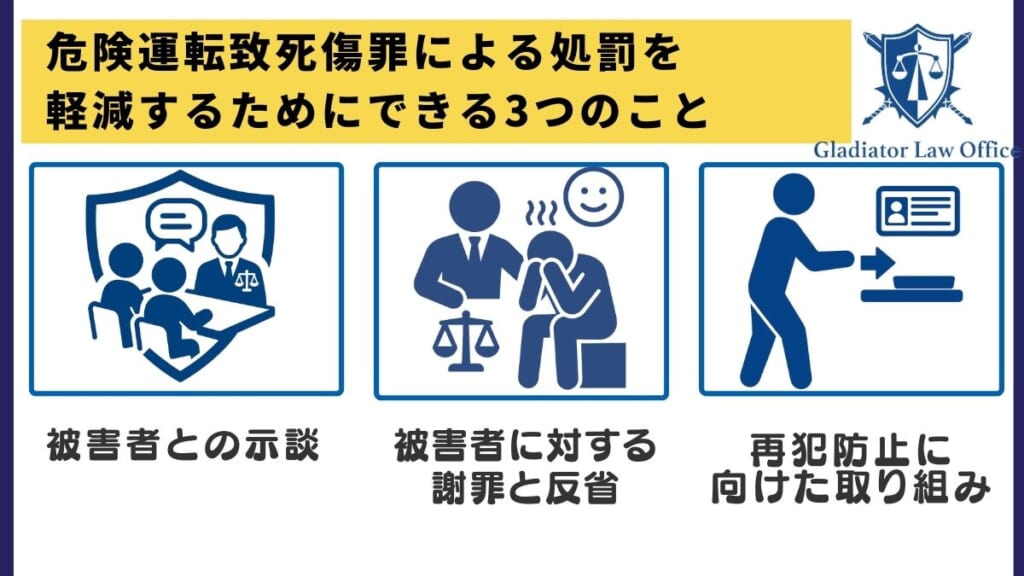
危険運転致死傷罪は、非常に重い法定刑が科される犯罪であり、有罪となれば懲役(拘禁刑)が避けられません。しかし、すべての事件が一律で実刑になるわけではなく、被害者の処罰感情や事故後の対応によっては、刑の減軽や執行猶予の可能性もあります。
以下では、処罰を軽くするために取り組むべき3つの具体的な方法を紹介します。
被害者との示談
もっとも効果的な対処法のひとつが、被害者との示談成立です。示談とは、被害者に対して金銭的な賠償を行い、加害者の刑事責任について一定の理解や許しを得る合意を交わすことです。
刑事事件において被害者と示談をするメリットには、以下のような点が挙げられます。
| ・被害者の処罰感情が和らぐ ・被害届の取り下げや厳罰を求めない意思表示が得られる ・裁判官の量刑判断に影響する |
特に、初犯であり、被害者が重篤な後遺障害を負っていない場合には、示談が成立することで起訴猶予や執行猶予付き判決になる可能性も高まります。
被害者に対する謝罪と反省
誠意ある謝罪と深い反省の意思を示すことも、処罰軽減のためには欠かせません。刑事手続きにおいては、以下のような姿勢が評価されます。
| ・被害者に対する謝罪文の提出 ・被害回復に向けた真摯な努力 ・法廷での反省の言葉や態度 |
形式的な謝罪ではなく、どれだけ自分の行為を重く受け止め、今後どう生きていくかを真剣に表明することが重要です。裁判官は「真摯な反省が見られるか」を情状として慎重に判断します。
再犯防止に向けた取り組み
同様の事故を二度と起こさないための具体的な再発防止策を講じることも、刑事裁判では有利な情状として考慮されます。
たとえば、
| ・任意での免許返納 |
| ・アルコール依存・薬物依存の治療や通院 |
| ・安全運転講習への参加 |
| ・生活環境の改善(転職・引越し等) |
などの取り組みを、弁護士と連携して記録・証明しておくことで、「再犯のおそれが低い」「更生の意欲が高い」ことを主張できます。
危険運転致死傷罪と罰金に関するよくある質問(Q&A)
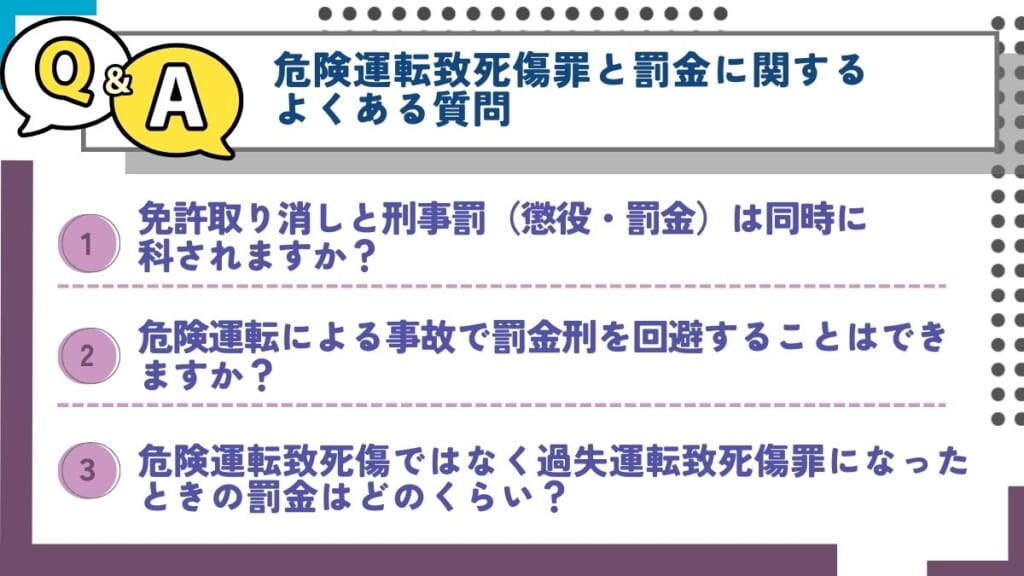
ここでは、危険運転致死傷罪に関して特によく寄せられる「罰金との関係」や「免許処分」「他の罪との違い」などの疑問にお答えします。刑罰に直結する重要なポイントですので、ぜひ確認しておきましょう。
免許取り消しと刑事罰(懲役・罰金)は同時に科されますか?
免許取り消しと刑事罰はそれぞれ別の制度であり、同時に科される可能性があります。
免許の取消や停止は行政処分であり、公安委員会によって判断されます。一方、懲役刑(拘禁刑)や罰金刑は刑事処分として裁判所が決定します。
たとえば、危険運転致死傷罪で起訴され有罪になれば、刑事裁判で懲役刑(拘禁刑)が科され、別途、運転免許も取消となるのが一般的です。
また、行政処分による免許の再取得には「欠格期間(最長10年)」が設けられ、免許の再取得が長期間できなくなることもあります。
危険運転による事故で罰金刑を回避することはできますか?
危険運転致死傷罪ではなく過失運転致死傷罪が適用され、怪我の程度が軽微、示談成立、初犯などの事情があれば不起訴処分になる可能性もあります。
そのためには、危険運転致死傷罪の適用を争うことが必要不可欠です。
危険運転致死傷ではなく過失運転致死傷罪になったときの罰金はどのくらい?
過失運転致死傷罪が適用された場合の罰金額の相場は、以下のとおりです。
| ・軽微な人身事故(打撲・捻挫など)……10万円〜30万円程度 ・中程度の傷害事故(骨折など)……30万円〜50万円程度 ・示談済の死亡事故や後遺障害事故……70万円〜100万円程度 |
これはあくまで一例であり、個別の事情によって大きく変動します。弁護士に相談することで、罰金刑で済む可能性を高めたり、金額を軽減できる場合もあります。
罰金刑のない危険運転致死傷罪を犯してしまったときはグラディアトル法律事務所に相談を
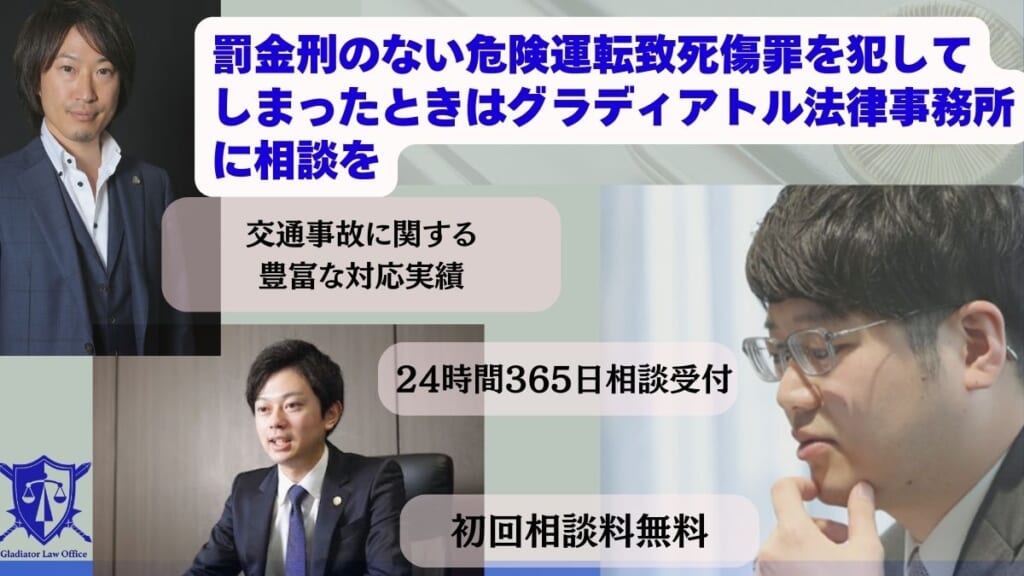
危険運転致死傷罪には罰金刑がなく、有罪となれば必ず懲役(拘禁刑)が科されます。そのため、「事故を起こしてしまったが、せめて罰金で済ませたい」と願っても、危険運転致死傷罪が適用される限り、その望みは法的には叶いません。
しかし、危険な運転行為だったとしてもすべての事件に危険運転致死傷罪が適用されるわけではありません。実際には、事故の内容や被害者のけがの程度、過去の前歴、示談の有無、本人の反省の程度など、多くの事情が刑事処分に影響を与えます。たとえば、運転態様が危険運転に当たらない可能性がある場合や被害が比較的軽微で示談が成立している場合には、より軽い「過失運転致死傷罪」として罰金刑や不起訴処分が選択されることもあり得ます。
このような判断は、本人の言い分をただ主張するだけでは認められにくく、法的観点から主張や証拠を整理し、適格に裁判官に伝えていくことが求められます。そこで重要になるのが、刑事事件に精通した弁護士のサポートです。専門知識に基づいて、危険運転の成立を争ったり、情状を整理して示談交渉を進めたりと、少しでも処罰を軽くするための最善策を講じてくれるのが弁護士の役割です。
グラディアトル法律事務所では、交通事故や危険運転致死傷罪の弁護経験を持つ弁護士が在籍しており、早期の相談から示談交渉、裁判対応まで一貫したサポートを行っています。ご本人だけで抱え込まず、まずは弁護士にご相談ください。状況に応じた最善の対応策をご提案いたします。
まとめ
危険運転致死傷罪は、罰金刑の規定がなく、成立すれば原則として懲役刑(拘禁刑)が科されます。そのため、処罰を軽くするためには、危険運転の成立を争い、過失運転致死傷罪の適用を目指すことが重要です。さらに、示談や謝罪、再発防止策といった情状面の対応も有利な処分を目指すなら不可欠です。
少しでも処罰を軽くしたいと考えるのであれば、早い段階で刑事事件に強い弁護士へ相談することが有効ですので、まずはグラディアトル法律事務所までお気軽にご相談ください。