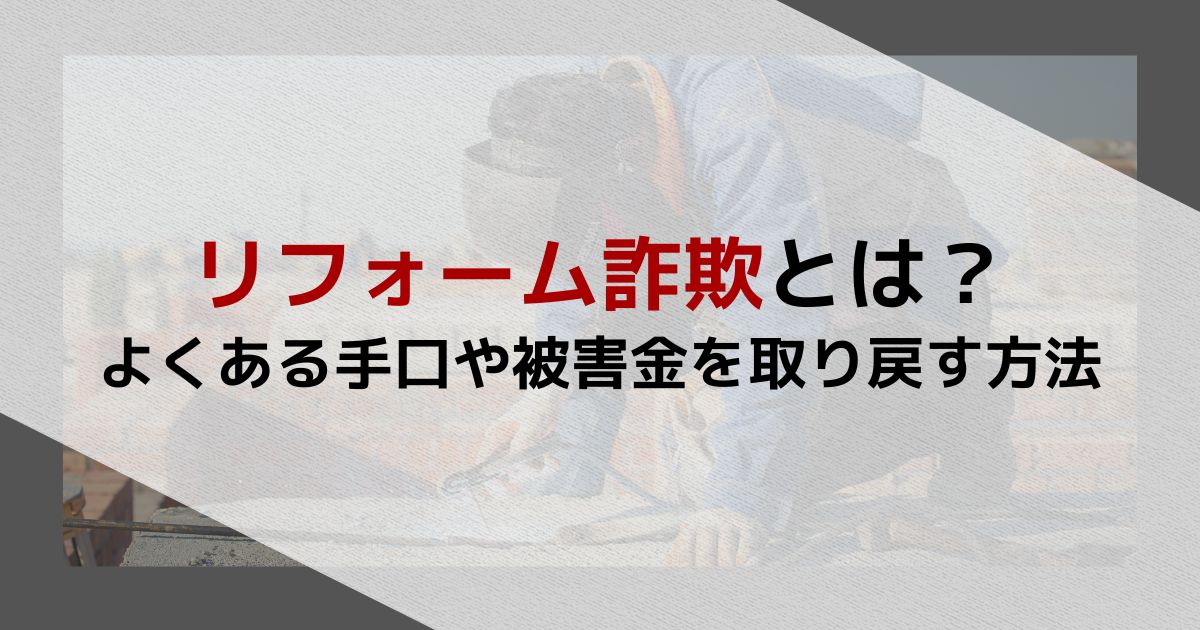「飛び込み営業に押し切られてリフォームの契約をしたけど、騙されていないか不安…」
「リフォーム詐欺に騙された場合はどうすればいいのだろう…」
近年、必要のないリフォームを勧められ、不当に高額な費用をだまし取られる詐欺事件が多発しています。
いわゆる「リフォーム詐欺」と呼ばれるものであり、匿名・流動型犯罪グループ「トクリュウ」が関与しているケースも多いようです。
実際、リフォーム詐欺の被害に遭い、今後どう対処していくべきなのか頭を悩ませている方もいるのではないでしょうか。
そこで本記事では、リフォーム詐欺のよくある手口や被害金を取り戻す方法について解説します。
リフォーム詐欺に騙されないためのポイントなどもわかりやすくまとめているので、参考にしてみてください。
リフォーム詐欺とは?
リフォーム詐欺とは、住宅の修理・改修を名目にリフォームを勧め、不当に高額な費用をだまし取る詐欺行為です。
リフォーム詐欺の特徴は、住宅に対する知識不足につけ込む点にあります。
「屋根が壊れている」「このままでは危険」と警告されると、事実かどうかわからない状態でも、焦りや不安の気持ちからついつい契約に踏み切ってしまうのです。
なお、訪問販売によるリフォーム工事・点検商法は年々増加傾向にあります。
自分自身が詐欺の対象になる可能性も十分あるので、常に疑いの気持ちを持つことが大切です。
リフォーム詐欺のよくある手口
次に、リフォーム詐欺のよくある手口を解説します。
自身の状況を振り返り、類似する部分がある場合は、リフォーム詐欺を疑ったほうがよいかもしれません。
点検中に屋根や設備を壊されて修理を勧められる
よくあるリフォーム詐欺の手口は、業者が屋根や設備を意図的に壊し、修理を勧めるパターンです。
具体的には、「無料で点検します」と突然訪問し、住人を屋根が見えない場所で待たせている間に、業者自身が屋根の瓦や板金を破損させます。
その後、「このままでは雨漏りする」「危険なので早急に修理が必要」と不安をあおり、高額な工事契約を迫るのです。
素人では故意に破損されたものかどうかを判断できないので、業者の言葉を鵜呑みにし、契約に応じてしまう人も少なくありません。
架空の不具合を指摘されて不必要なリフォームを勧められる
リフォーム詐欺では、架空の不具合を指摘され、不必要なリフォーム工事を勧められるケースも多く見受けられます。
屋根や床下などは普段目にしにくい部分であるうえ、本当に不具合が起きているかどうかを素人が判断することは簡単ではありません。
そのため、「屋根に大きなひび割れがある」「シロアリ被害が進行している」などと根拠のない説明をされても、詐欺だと気づきにくいのです。
架空の不具合を指摘する詐欺は年々増加しており、特に高齢者が狙われやすい傾向にあります。
補助金・保険で負担を抑えられると嘘をつかれる
「補助金・保険で負担を抑えられる」と嘘をつくのも、リフォーム詐欺のよくある手口です。
具体的には「国の補助金が利用できる」「火災保険でリフォーム費用が実質無料になる」などと説明され、契約を迫られます。
リフォームに対して適用できる補助金・保険があるのは事実ですが、複数の条件が定められているはずです。
適用条件を確認しないままリフォームを進めてしまうと、結局、全額自己負担しなければならない状態に陥ってしまいます。
契約後に適切な工事がおこなわれない
契約後に適切な工事がおこなわれない場合も、リフォーム詐欺を疑ったほうがよいでしょう。
悪質業者の目的はリフォーム費用を受け取ることなので、契約さえできれば、あとは適当に工事を済ませようとしてくるのです。
場合によっては、工事が始まらないまま連絡が途絶えるケースもあります。
追加工事で費用を吊り上げられる
追加工事を理由に費用を吊り上げられるのも、リフォーム詐欺の典型パターンといえるでしょう。
基本的な流れとしては、まず安い見積もりを提示され、安心したところで契約を結ばされます。
しかし、工事が始まると「想定外の不具合が見つかった」「この部分も今のうちに直さないと危険」などと追加工事を提案され、高額な費用を請求されてしまうのです。
さらに悪質な場合は、業者の提案を受け入れるか迷っていると、「作業が遅れたので追加費用が発生する」などと主張されることもあります。
本当に追加工事が必要なケースもありますが、業者からの提案を鵜呑みにすることはおすすめしません。
逮捕事例・判例からみるリフォーム詐欺の実態
ここでは、逮捕事例・判例をもとに、リフォーム詐欺の実態をみていきましょう。
| 事案概要 |
|---|
| 必要のない屋根のリフォーム工事で現金をだまし取ったとして、福島県警は6日、リフォーム会社「〇〇」(埼玉県新座市)社長(23)(詐欺未遂で起訴)を詐欺容疑で再逮捕し、愛知県半田市、自営業の男(24)を同容疑で逮捕した。2人の認否は明らかにしていない。発表によると、2人は今年5月上旬頃、南相馬市原町区の70歳代男性宅を訪れ、「本格的に修理を行った方がいい」「いつ雨漏りしてもおかしくない」とうそをついて屋根の修理工事を行い、男性から工事代金として50万6000円をだまし取った疑い。2人はSNSなどでつながった「匿名・流動型犯罪グループ(トクリュウ)」のメンバーで、工事は別の人物が行っていた。(引用:読売新聞オンライン) |
| 「屋根の一部が壊れている」などと偽り、リフォーム代金をだまし取ろうとしたとして、埼玉県警は12日、詐欺未遂と特定商取引法違反(不実の告知)容疑で、リフォーム業者「〇〇」(埼玉県川口市)の代表〇〇容疑者(27)=同市金山町=ら10人を逮捕した。認否は明らかにしていない。・・・他に逮捕されたのは、同社の幹部3人と、飛び込み営業をする「アポインター」3人、その後、契約を締結する「クローザー」3人の計9人。(引用:時事通信) |
| 埼玉県のリフォーム会社の役員、〇〇被告(24)は、去年5月、南相馬市の女性の自宅を訪れ、「屋根の修理をしなければ雨漏りするおそれがある」などと必要のない修繕工事を持ちかけて、工事代金として161万円あまりをだまし取ろうとしたなどとして詐欺未遂などの罪に問われました。・・・〇〇被告に懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。(引用:毎日新聞) |
摘発が相次ぎ、社会問題化している今でも、リフォーム詐欺に騙されてしまう人は多いので、十分に注意してください。
リフォーム詐欺に騙されないためのポイント
次に、リフォーム詐欺に騙されないためのポイントを解説します。
飛び込み営業には応じない
リフォーム詐欺に騙されないためにも、飛び込み営業に応じないようにしましょう。
飛び込み営業で不安をあおり、必要のない工事を迫るのはリフォーム詐欺のよくある手口です。
たとえば、業者の身なりをした人物が突然現れ、「通りがかった際に屋根の破損が気になった」「無料で屋根の点検をします」などと言われたときは詐欺の可能性があります。
いくらせかされても、その場で契約してはいけません。
本当にリフォームの必要があるのか、信頼できる業者に確認することが大切です。
複数の業者から見積もりを取る
複数の業者から見積もりを取るのも、詐欺被害を防ぐ有効な方法といえるでしょう。
突然訪問してきた業者から見積もりを提示されたところで、専門的な知識がなければ、適正価格かどうかを判断することはできません。
その点、複数の見積もりを取って比較すれば、不当に高い費用を請求されていることに気づける可能性があります。
また、優良な業者が現場確認をおこなうなかで、そもそも工事の必要がないことを指摘してもらえるケースもあるでしょう。
業者の信頼性を事前に調べる
リフォーム詐欺に騙されないためには、業者の信頼性を事前に調べることも重要です。
具体的には、以下のような点を確認しておくとよいでしょう。
- ホームページはあるか
- 施工実績は十分か
- 事業者団体・業界団体に加盟しているか
- 公的な資格保有者がいるか
- 過去に不祥事を起こしていないか
- 口コミは悪くないか
また、担当者と話すなかでも、信頼性をある程度見極めることができます。
たとえば、料金の説明が不十分な場合や、都合のいいことばかり並べてくるような場合は信頼性に欠けるため、リフォーム詐欺を疑うべきです。
納得できるまで契約書の内容を確認する
リフォーム詐欺に騙されないためにも、契約書の内容は納得できるまで確認しましょう。
工事内容・金額・支払方法・保証内容などが曖昧なまま契約すると、仕上がりが想定と異なったり、追加費用を請求されたりする可能性があります。
一方の利益を不当に害する契約書は原則として無効になるものの、そこにサインしている以上、不利な立場に立たされる可能性も否定できません。
少しでもわからないことがある場合は、その場で契約せず、業者に確認を求めたり、第三者に相談したりする姿勢が重要です。
リフォーム詐欺の被害金を取り戻す方法
ここでは、リフォーム詐欺の被害金を取り戻す方法を紹介します。
主に3つの方法があるので、それぞれ詳しくみていきましょう。
クーリングオフ制度を利用する
リフォーム詐欺に騙された場合は、まずクーリングオフ制度を利用できないか確認しましょう。
クーリングオフ制度とは、契約後一定期間内に限り、無条件で契約を解除できる制度のことです。
リフォーム工事に関しては、主に以下の条件を満たした場合にクーリングオフ制度を利用できます。
- 訪問販売や電話勧誘販売によって契約を締結したこと
- 契約締結場所が施工業者の営業所以外の場所であること
- 契約書面を受領した日から起算して8日以内であること
たとえば、飛び込み営業でリフォーム工事を契約してしまった場合でも、8日以内に書面やメールでクーリングオフの意思を伝えれば、契約はなかったことになり、支払った代金も返金されます。
悪質な業者は理由をつけて拒否してくるかもしれませんが、クーリングオフは消費者の権利なので、毅然とした態度で手続きを進めるようにしましょう。
直接交渉で返金を求める
クーリングオフ制度が利用できない場合は、業者と返金に向けた交渉を進めていくことになります。
返金を求める際は、内容証明郵便を用いるケースが一般的です。
内容証明郵便を用いれば、本気度や裁判を視野に入れている姿勢が伝わるので、業者が返金に応じる可能性が高くなります。
ただし、被害者本人と業者が直接交渉することはおすすめしません。
一般人と業者では、契約行為や工事に関する知識量が違うこともあり、言いくるめられるおそれがあります。
また、悪質な業者を相手にすると二次被害が生じるリスクもあるので、返金交渉は弁護士に任せるのが賢明な判断といえるでしょう。
裁判を起こす
業者との交渉が難航した場合は、裁判を起こすことも検討するべきです。
民事訴訟を提起し、裁判所から返金を命じる判決が下れば、業者が支払いを拒んだとしても、相手の財産を差し押さえることができます。
ただし、手慣れた詐欺業者は強制執行を想定し、騙し取ったお金を隠していることも多いです。
勝訴したからといって、必ずしも全額回収できるわけではない点に注意しておく必要があります。
また、裁判を起こすには、証拠の収集や裁判所とのやり取りなど、膨大な手間と時間がかかります。
個人で対応するのは現実的ではないため、弁護士のサポートが必要不可欠です。
リフォーム詐欺に遭った場合の相談先
リフォーム詐欺に遭った場合の主な相談先は、公的窓口・警察・弁護士の3つです。
対応してもらえる範囲に違いがあるので、それぞれの相談先をうまく活用しましょう。
なお、個別具体的な返金手続きに対応してくれるのは弁護士だけです。
一貫したサポートによって返金の可能性を少しでも高めたいのであれば、弁護士に相談することをおすすめします。
公的窓口
リフォーム詐欺に遭った場合は、公的な相談窓口に相談してみるのもひとつの方法です。
専門知識を持つ相談員が状況を整理したうえで、適切な解決策を提案してくれます。
具体的には、国指定の相談窓口「住まいるダイヤル」や各地域にある消費生活センターなどが挙げられるでしょう。
ただし、公的窓口に相談しても、返金手続きに対応してもらうことはできません。
基本的には、今後の対応方針に関する大まかなアドバイスを受けられるだけです。
警察
リフォーム詐欺に遭った場合は、警察に相談することも大切です。
リフォーム詐欺は詐欺罪などの犯罪に該当するため、警察に相談すれば捜査の対象にしてもらえる可能性があります。
たとえば、業者と音信不通になった場合でも、警察が動けば居場所を突き止めることができるかもしれません。
ただし、被害を証明できる証拠がなければ、被害届や告訴状を提出しても受理してもらえません。
また、返金に関する民事上の問題に関しては、警察の協力を得られない点に注意してください。
弁護士
リフォーム詐欺に遭った場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
被害金の返金手続きを任せられるのは、弁護士だけです。
弁護士に相談・依頼すれば、業者との返金交渉や訴訟に関することを一貫して任せられます。
直接業者とやり取りする必要がなくなるので、精神的な負担も大幅に抑えられるでしょう。
ただし、詐欺事件の解決には高度な知識と経験が求められるため、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。
詐欺事件を得意とし、解決ノウハウを有する弁護士に相談することが重要です。
グラディアトル法律事務所では、実践経験豊富な弁護士が24時間体制で相談に応じています。
詐欺被害に遭った方はもちろん、「もしかしたら詐欺かも…」と疑っている段階の方も不安に感じることがあれば、お気軽にご相談ください。
まとめ
リフォーム詐欺の摘発件数は増加傾向にあり、自分自身が被害者になる可能性も十分あります。
そのため、まずはリフォーム詐欺への対抗手段を身につけ、騙されないようにすることが大切です。
仮にお金を騙し取られたとしても、簡単に諦めてはいけません。
適切に法的手続きを進めれば、被害金を取り戻せることもあります。
ただし、悪質な業者を相手にするのはリスクが大きいので、返金に関することはできるだけ弁護士に任せるようにしましょう。
グラディアトル法律事務所は、詐欺事件を得意としている法律事務所です。
初回相談は無料、LINE相談も随時受け付けているので、困ったときはいつでもお問い合わせください。